いい漫画編集者ってなに?
編集者座談会
顔出しNGだから本音を語り合える!?
新人×ベテラン編集者による座談会!
-
G.K.
2016年入社
ヤングチャンピオン編集部
副編集長前職は成年向け漫画の編集者。編集長として新雑誌を創刊するなど成年漫画編集としての上限が見えてきた時に秋田書店の募集を見つける。「刃牙」をはじめ秋田書店の様々な漫画に親しみがあったことから応募し、入社。
-
Y.Y.
2008年入社
プリンセス・ボニータ編集部
編集長就活当時に秋田書店の漫画にハマっていたことから「秋田書店の漫画をもっと知ってほしい」と営業を志望。山手線や東海道五十三次の書店回りをして平積みされているコミックのリストを提出するなど積極的な姿勢が評価されて入社。
-
K.T.
2024年入社
少年チャンピオン月刊誌
編集部中学生の頃から週刊少年誌の編集者に憧れを持ち、就職活動では4大週刊少年誌を発行する出版社すべてにエントリー。その中でも秋田書店は面接で自分を一番見てくれたことに感銘を受けて入社。
-
01
漫画編集者の仕事とは?
-
中高生の頃は、「編集者は漫画家さんと打ち合わせして一日が終わるんだろうな」って漠然とイメージしていましたが、雑誌って次号予告や付録ページといった漫画以外のページがたくさんありますよね。「この編集作業は新人が通る道だよ」と言われて、「こんなこともやるんだ」ってびっくりしました。
自分も漫画編集者は漫画だけ作っていると思ってましたね。自分が所属しているヤングチャンピオン編集部は青年誌なので新人はグラビアページも担当しますよ。さすがに企画まではしないけど、撮影現場で先輩をサポートすることから始まります。
プリンセス・ボニータ編集部も基本的には漫画以外のページの版下作業からスタート。例えば、次号予告のページならすべての作品に触れる機会があるので、雑誌にどんな作品が掲載されているか理解するきっかけになりますし、どの作品をメインにするかなどレイアウトの基本も学べます。それとプレゼントページも新人が担当します。

-
ちょうど今、月刊少年チャンピオン/別冊少年チャンピオン/月刊チャンピオンREDのプレゼントページは僕が担当させていただいています。漫画ページに比べて自由度が高く、先輩からも「好きにやっていいよ」と言われています。それこそプレゼントする賞品も自分で考えて発注していますし。プレゼント目当てで購読してくれるだけでも嬉しいので、「どんな賞品をプレゼントしたら読者は喜ぶだろう?」と考えながらコツコツ頑張っています。
責任もってやっているのは偉い!版下作業やりつつ、先輩が打ち合わせしているのを盗み聞きしながら「作家さんとこんな風に打ち合わせしているのか」「ネームってこうやってチェックするんだ」って勉強していくみたいなところがあります。それからサブ担当になったり、ベテラン先生の担当を引き継ぎながら成長していきますね。

-
先輩の仕事を見るのは重要ですよね。ヤンチャン編集部には「ケツ持ち制度」があるんですよ。さすがに新人一人に企画させたり、作家さんと打ち合わせするということはなくて、まずは先輩や上司と組んで企画を起こして通すところまで経験してもらいます。あとは、Y.Y.さんがおっしゃるようにベテランの先生から勉強させてもらったり、連載が順調に回っている作品を引き継いで仕事を覚えてもらう感じです。
僕はサブ担当の経験がなくて、今はメイン担当として数作品引き継がせていただいています。それこそベテランの先生ばかりでとても勉強になっています。ネームのやり取りは何となくできるようになりましたが、メディア化の話があるとか作品が賞をもらった場合など、通常の連載がある中でどのように先輩たちが進めているのかよく分からなくて…。

-
確かに。私が担当している『海が走るエンドロール』はありがたいことに「このマンガがすごい!2022」でオンナ編1位に選んでいただきました。その時は宣伝物や販促物の確認が増えましたし、メディア対応に追われてました。また、担当作がアニメ化した際には1日中ずっと関係者とメールのやり取りをしていました。本当に自分でも何をしているのかわからないまま、ワーっとやってきました。アニメ化の経験はG.K.さんもありますよね?
ありますよ。メールのやりとりや各所への確認作業が一気に増えて大変です。まあ、急に仕事が増えたとしても漫画家さんも編集者も何とかこなせるようになりますよ(笑)。やらなければいけない仕事ってあるじゃないですか、先にそれを終わらせちゃえばいいんです。必用に応じてできるようになるから。たぶん。

-
作家さんにとって作品がメディア展開されるのってどうなんですか?もちろん作品が売れるのは分かるのですが…。
日常を舞台にした作品とかだと、「アニメの放送が終わったら漫画作品も終わる」と間違って認知されてしまう可能性もあったり。
そうなんですよ。アニメが終わったらブームも去っちゃうみたいなところもあります。だから、メディア化する場合は、最終回を迎えるタイミングを合わせることも最近は多いです。

-
それとメディア化した作品のクオリティが低かったりすると、漫画家さんがダメージを受けちゃうこともあります。けれども、すでに進んでいるとどうしようもないです。
そういう時は、アニメ化やドラマ化などをやめるって決断するんですか?それとも編集の力でさらに良くするとか?
メディア化はとても大勢の人間が関わっているので、進んでしまったら中断も大幅な修正も難しいと思います。だから、漫画家さんにはリスクについても説明しておくことが大切です。
基本的に漫画家さんって、「アニメ化の話があります」と言われたら嬉しく感じる人が多いと思うのですが、やっぱり自分の作品を預ける以上、親心もあって素晴らしいものに作ってもらいたいと思いますよ。

-
-
02
編集者でうれしかったことは?
-
僕は二つありまして、一つが自分の担当している新人漫画家さんが「新人まんが賞」に入賞されて、「これからもK.T.さんと一緒に作品を作っていきたいです」と言われた時は嬉しかったです。もう一つが、芸人さんのコラムを担当していて、自分の会いたい芸人さんと一緒に仕事したり、芸人さんと漫画家さんとの対談などいろんな企画を自由に考えさせていただけることが嬉しいです。もちろん、企画から進行管理までやらなければいけないので大変ですが。
自分の興味があることに対して企画を立てて動けるというのは本当にいいと思いますよ。だってK.T.くんが担当じゃなかったら、ほかの人がイヤイヤやっていたかもしれない。
G.K.さんが嬉しかったことって何ですか?

-
あんまりないかなあ…。
なんでこの仕事しているんですか?(笑)
いや、嬉しいことは色々あるんですけど(笑)
大変なことが9で、良いことは1くらいじゃないですか?その1が嬉しくて仕事の原動力になっているんですけど、「超嬉しい」というのはなくて、なんか「ちっちゃな嬉しい」がいっぱいある感じ。
-
作品が売れた時とか?
それはもちろん。それとポジティブな感想を見た時や、コミックスのデザインや構成がいい感じにできた時とか。
私は作品が売れたことで先生の生活が潤った時ですね。さらに会社としても潤うし、みんながハッピーになりますから。

-
漫画の人気が出て関係者も読者もみんなが潤うのは一番嬉しいことですよね。
やっぱり漫画は薄利多売なので、作家さんが描いたものを多くの人に届けるというのが編集者の仕事の一つですから、作品の知名度が上がっていろんな方が読んでくださるのは本当に嬉しいことです。

-
-
03
面白い作品、愛される作品を生み出すコツは?
-
私たちこそ知りたいです(笑)
僕は、「その作家さんが描きたいものを描かせてあげること」なんじゃないかと思っているのですが、どうでしょうか?
作家さんによります。その作家さんが得意だと思っていることが本当に得意かどうか分からないので。「私はアクションが得意だ」と思っている人がいても、実際は「ラブコメのほうが得意だよ」みたいなことも普通にあるから。

-
作家さんがやりたいことを聞いたうえで、K.T.くんから「でも自分としてはあなたのこういうところが凄くいいと思います」とその部分を盛り上げたほうがもしかしたら面白い作品が生まれるかもしれない。
作家さんと話をして、どうしたら売れる作品を作れるか判断するということですね。
天才タイプの作家さんなら何もいじらないほうがいいかもしれないけど、「ちょっとこうしたほうが分かりやすくなるな」ということってあるんです。そこを引き上げてあげると面白い漫画になるのかなと思います。私、入社一年目に読み切り作品を担当したところ、先輩から「これが面白いと思っているのはY.Y.だけだよ」と言われ、悔しくなったことがあって。でも、今思うと独りよがりというか外に向けて作っていなかったんだなと。ただ、自分が本当に面白いと思っていた部分については、人から言われてどんどん変えてしまうと何が面白いのか分からなくなってしまうので、そういう時は、「自分はこれが好きだった」と立ち返ることが大事だと思っています。

-
面白い作品と、愛される作品って違いますか?
愛される作品というのは、キャラクターが魅力的かどうかがポイントな気がしますね。
漫画家さんが愛されているケースもあります。漫画家さん自身にファンがついていて、その人の描いた漫画だったら全部読むとか。

-
ありますね。前の作品の部数が出ていると、新しい挑戦もしやすいとか。でも最近は作家買いが減っている気がします。やっぱりキャラかな。キャラにファンがつくと続きを買ってずっと読みたくなると思うんですよ。さらにグッズも買ってくれるので展開しやすかったりとか。
確かに、作品の寿命は確実に伸びますよね。
そういった愛されるキャラを作るにはどうしたらいいですか?

-
それはすごく難しい。例えば、昔メガネ男子が流行っていた時があったんですが「オーソドックスに頭がよくてちょっとクールなキャラを出しておけばいいでしょ」ということでもなく。ゲーム的なキャラ設定と漫画のキャラ設定は違うんですよね。やっぱり、漫画家さんがよくおっしゃっているように、「キャラが勝手に動き出す」というレベルになるのがまず第一な気がします。
「キャラが勝手に動き出す」という考えは大事ですよね。自分は、「キャラクターで二次創作できるか」をキャラが生きているかどうかのバロメーターの一つにしています。なんでもいいんですけど有名作品の中にキャラを放り込んだ時に、その作品の人気キャラと張り合えるかとか、このキャラはこんなシチュエーションならどう動くか想像できるかが、キャラが生きているかどうかの指針になります。そんなキャラを作るためにはやっぱり人間としての掘り下げが大事だと思います。

-
それともう一点あって、最終回が良い作品は手元に置いてずっと読みたくなるんですよ。作品が終わってからも、いろんなグッズ展開やミュージカルになったりするくらい愛されますので。
逆に最終回が物議を醸す作品もありますね…。
そうなると、「最後がこれならもう買わなくていいや」ってなっちゃう。追いかけ続けてくださった読者のためにも、最後はちゃんとしたいなって思いはいつもあります。もちろん、早めにたたまなくてはいけなくなり漫画家さんの希望する最後にならないこともありますが。

-
作家さんが希望する最後まで、長く描き続けられるということは大切ですし、我々もそこを目指したいですよね。
それをするために愛されるキャラを作ってあげる。そうすると続きが読みたくなるはずですから。

-
-
04
いい編集者になるためには?
-
僕は、「いい編集者って、いい社会人」なんじゃないかなと思っていまして。版下作業や漫画家さんとのやり取りも社会人スキルがなければできませんし、まずは普通にコミュニケーションが取れるようになることが第一歩かなと。僕自身、まだ一歩目の段階なので解像度を上げられていないのですが…。
新人でそこまで考えているなんて、うちの編集部に欲しいくらい。
そういえば、2か月ほど前、新宿の飲み屋さんでY.Y.さんを見かけたことがありまして。
え??知らない。

-
僕はカウンター席で一人で飲んでいましたが、隣にY.Y.さんがいて女性の方とお話されていました。
あ!デザイナーさんと飲んでいた。
会話が白熱されていたので声をかけられなかったのですが、Y.Y.さんの姿を見てやっぱりコミュニケーション力が凄い高いなって感じました。
怖いなあ(笑)

-
自分はまだ一歩目なのでコミュニケーション力ぐらいしか思いつかないのですが、ぜひみなさんからその先を知りたいです!
やっぱり周りに信頼される人がいい編集者じゃないかな。会社側と漫画家側のどちらにも立ちすぎない。会社の都合だけに寄りすぎると編集者ではなくなると自分は思うし、漫画家さんの都合しか考えないのであれば会社に所属せずフリーの編集者になればいいので。

-
いろんなやり方がありますが、私は「陰の者」として作家さんと作品をいかに一番に考えてあげるかどうかが大事だと思いますね。あと、「面白がり力」があるかかな。
「面白がり力」?
面白いところを見つけられるかとか、こうしたら面白くなるんじゃないかとか。つまらないといわれる映画を観た時でも「ここは面白かった」と感じたり、逆に「こうしたら良かったのでは?」と考えるとか。それと、何かしらのオタクであったり、何にでも興味を持てる人でもいいと思う。また、ハブとして会社や作家さんなどいろんな関係者と柔軟につながれることも大事ですよね。

-
編集者って何でも屋であり、便利屋ですね。
そうそう、打ち合わせだけで終わるなんてフィクションの世界(笑)。
編集者を扱った作品によくある気がするシーンで、何か大きめの仕事が一つ終わったら「やったー!終わったー!」みたいになるじゃないですか。そんなこと一生ないですよ(笑)。だって、10以上並行して仕事していますから。
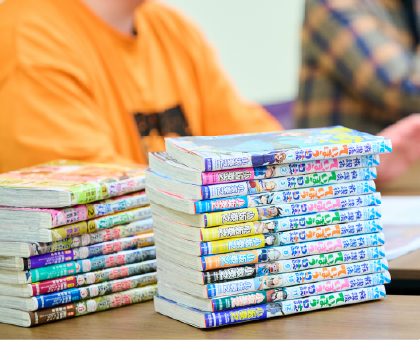
-
昔、先輩から言われたことで「一人で雑誌を作れるぐらいの作家さんを持っておいたほうがいい」と言われました。K.T.くんも、他誌に描いている作家さんなどいろいろと声がけしたらいいと思います。歴史ある秋田書店の編集者という肩書きって強いですよ。「今度こういう仕事しませんか?」と声をかけても、絶対にないがしろにはされないはずです。もし断られても、別のタイミングで声をかけたら「やりましょう」と言っていただけるかもしれませんし。そういうことを怖がらずにできる人がいい編集者なのかもしれないです。
確かにそうですね。それこそ子どもの頃から週刊少年誌を読んで育ちましたが、「少年チャンピオン」という名前はとても大きな肩書きですね。

-
-
05
秋田書店の雰囲気って?
-
いよいよ飯田橋本社も見納めですね(注:2025年2月現在、建て替え工事中)。最後は壮大に破壊したいです(笑)。
「刃牙の家」みたいな感じで(笑)
(爆笑)。
みなさんは秋田書店ってどんな雰囲気の会社だと思いますか?編集部はなんか変な人というか個性的な人が多い。自由というか風通しがいい会社だと思います。
Y.Y.さんはどう思いますか?

-
G.K.さんの言う通り、自分が変だということを気にせず生きていけるみたいなとこはありますね。みんな個性的なので、「ここにいていいんだ」って感じる会社(笑)。あとはそうですね、秋田書店は基本的に漫画が好きな人が多いのと、邪悪な人間がいない。
大丈夫ですか?忖度していません?(笑)
嫌なことをしてくる人はいない、と信じたい(笑)。それと「やってやるぜ」みたいなところがありますよね。とにかくやってみて、失敗したらそこでは反省するけど「さあ、次」みたいな切り替えが早い人が多いです。

-
伝統的に失敗に対して寛容ですよね。逆に成功しても何もないですけど(笑)。
評価をされるともらえる、社長賞が一応ありますよ。
社長賞として商品券をいただけますが、周りから「お前、いつ俺たちに還元してくれるんだよ」って言われるんですよ(笑)

-
還元できないように商品券になったらしいですよ。
換金してこいって言われます(笑)。あれ、何の話でしたっけ?そうそう、失敗に対して寛容なので遠慮して動かないよりはとりあえずやってみて失敗したら反省するというサイクルのほうが絶対得だと思いますね。
僕、まだ入社して一年も経っていませんが、「こんなことをやりたい」と言っても誰からもNOと言われたことが一度もないです。逆に「何かあったらそれは先輩の責任だから」と言ってくれることが多くて。配属されてまだ2か月もたたない頃、京都へ出張編集部に行く話があったのですが、先輩たちは校了と重なってしまって誰も対応できないことがあって。「僕一人で出張してきていいですか?」と聞いたら、「よし、編集部の看板背負って行ってこい」と言われました。NOと言われない風土ってすごく素敵です。
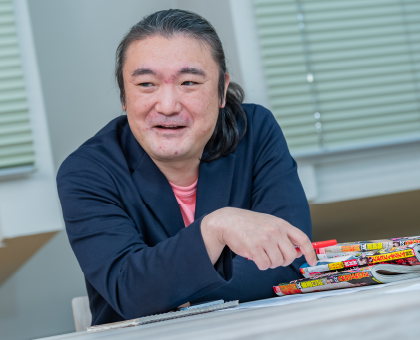
-
今の話を聞いていても、自分から行きたいと手を挙げてくれるのはありがたいですね。とても能動的な新人だ。
また、部署の垣根を越えた交流が多い会社だなと思いました。ほかの編集部の先輩からランチやお酒に誘っていただいたりと、編集部間の距離が近いのでいろんな話を聞けるのは秋田書店らしいかなって。
垣根はないと思うけど、交流の多さは人によるので、それはやっぱりK.T.くんが能動的だからだよ。

-
そうそう、部署の架け橋になっているもん。
そんなアットホームでNOと言わない雰囲気があるからこそ、自分から何かやりたいという思いのある人はこの会社に向いているのかなと思っています。それと企画がボツになっても立ち直る力がある人とか。
G.K.さんはどんな人が向いていると思いますか?
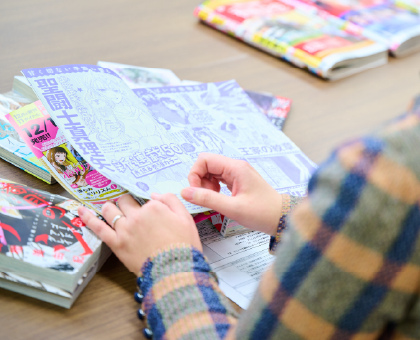
-
向いている人…。自分が思うのは漫画が好きで体力がある人。あとは裏方として作家さんのお手伝いをしたい人かな。編集が主役ではなくて漫画家さんが主役ですからね。そういったサポートに興味のある人はぜひ応募してほしいです。
秋田書店の社風かもしれないけど、編集者は前に出るというよりも「陰の者」としてあくまでも作品のサポートに徹することを大事にしていますからね。もちろん出なければいけない時は出ますが。ということで、今回は私たちが前に出過ぎないよう顔出しNGでお願いしますね(笑)。

-



